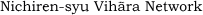|
|
「ビハーラ講習会」地方開催
|
|
立正安国・お題目結縁運動の項目にもなり、「ビハーラ」という言葉が随分と認識されて参りました。第二期育成活動に入ってからは、「ビハーラ活動の全国的展開」という項目が社会活動「但行礼拝」の中の「いのち」の活動に盛り込まれています。
ビハーラ活動とは、医療や福祉や地域社会との連携のもとに、寺院において、自宅において、あるいは病院や施設において、病気や障がい、高齢化に悩む人たちと苦しみを共にし、精神的、身体的な苦痛を取り除き、安心が得られるよう支援する活動のことです。日蓮宗のビハーラ活動は、法華経安楽行品に説かれる安楽の供養をはじめ、六波羅蜜、四無量心、四摂法の実践であり、すべての人々が仏の教えにふれて仏になることを願い導く、法華菩薩行であると位置付けられます。
NVN(日蓮宗ビハーラ・ネットワーク)は、日蓮宗のビハーラ活動を普及・推進するとともに、会員相互の情報交換と協力連携を図ることを目的とする、任意の団体です。「日蓮宗ビハーラ講座」「ビハーラ活動講習会」「ビハーラ活動実践講座」を受講した日蓮宗教師が中心になり、趣旨に賛同する方々で組織されています。
「ビハーラ講座」は平成八年度に第一回が開催されました。平成元年に開催された中央教化研究会議において、当時大きな社会問題としてクローズアップされていた脳死と臓器移植の問題や終末期医療のあり方などの生と死の間に生起した新たな課題、医療と宗教に関する諸問題について、仏教、就中法華教学の立場から検討する必要性が議論され、それらの諸問題について継続的に検討する組織として、平成二年に「日蓮宗医療問題研究会」(現「日蓮宗生命倫理研究会」)が発足しました。そこでの研究討議の結果、現代社会の中で、生・老・病・死の苦しみのただなかにある人々にどのような支援の手を差し伸べるべきなのか、日蓮宗徒として具体的な活動に踏み出すべきであるとの共通認識に至り、「お見舞いの手引」や高齢者向け教化資料「老いてこそ」の作成を行うと共に、福祉関係の教育機関や医療施設、緩和ケア施設、老人保健・福祉施設等の視察研修を経て、開催に至りました。
当初は試行的な要素も多く、現代宗教研究所の所管事業としてスタートしましたが、その後、ビハーラ活動の全国的展開と幅広い参加者を募る意味で、所管が伝道部に移管し「ビハーラ講習会」となり、平成十八年度からは社会教化事業に位置づけられ、ビハーラ活動の入門的講習を「社会活動講習会」で行い、実践的講習を「ビハーラ活動実践講座」で行うこととなりました。
以来、基礎的な面では、日蓮宗生命倫理研究会(日生研)と共に「心といのちの講座」を開催して仏教的生命観についての研鎖を深め、実践的な面では、檀信徒のお見舞い活動、家族への精神的なサポート、葬儀や法要におけるグリーフケアの実践、あるいはまた、医療施設、高齢者、障害者向け施設の運営等におけるビハーラ活動の実践を行ってきました。東日本大震災以降では、震災被災地への傾聴ボランティアの実践や、被災地寺院にハンドタオルを送る活動や研修会の実施等にも取り組んできました。
また、これまで積み重ねてきた講習会のカリキュラムの中で一貫して取り上げられてきた主要な内容のエッセンスを収録した『ビハーラ・ノート』を平成二十三年に出版しました。
このように、病気や障がい、高齢化に悩む人たちと苦しみを共にし、真の安心が得られるよう支援する活動として、そしてまた、法華菩薩行の実践としてのビハーラ活動を提唱し、講習会を開催して、混迷する現代社会にあって、「いのちに合掌」をスローガンに、「敬いの心で安穏な社会づくり、人づくり」を目標として推進する宗門運動、「立正安国・お題目結縁運動」の中で、ビハーラ活動は重要な一翼を担うものです。また、東日本大震災の被災者支援の観点からも、ビハーラ活動の主要な要素であるグリーフワーク、グリーフケアの重要性が指摘されています。大震災被災者の皆様方に対する長期的な支援活動は、大きな課題であり責務であると認識しているところです。
今日、日本社会は、未曾有の大震災、世界的に例を見ない少子高齢社会の進展という難題に加え、経済の低迷や文化的なアイデンティティの喪失といった深刻な問題を抱えています。その社会の中で、私ども仏教徒がいかに抜苦与楽の菩薩行を実践していくべきか、深刻に問われていると思います。様々な苦悩を抱え、悩み苦しむ人たちと苦しみを共にし、真の安心が得られるよう支援する活動としてのビハーラ活動は、今後ますます必要不可欠のものとなると思われます。
しかしながら、近年行われてきた宗務院でのビハーラ活動実践講座は参加者が少なくなってきました。一方、平成二十二年度に寺庭婦人・寺族も参加して高知で行われた「ビハーラ講習会in高知」や平成二十三年度に大阪で行われた「ビハーラ活動講習会in近畿」では、それぞれ四十名、六十名を超す参加者がありました。
今年度からは宗務院での講習会が無くなりました。そこでNVNでは、第二期育成活動の「ビハーラ活動の全国的展開」に合わせ、「ビハーラ講座」地方開催の為の提案を行っています。
講義例案として以下に九つの講義を挙げさせて頂いています。管区・教区、教師・檀信徒、あるいは寺庭・寺族等、対象のニーズに応じて、講義例案の組み合わせが可能となっております。半日、一日、一泊二日等の時間に応じて、講義コマ数と組み合わせの設定を自由にして頂けます。但し、講師の都合等によってご希望に添いかねる場合もありますので、ご了承ください。
過去に行われた地方での講習会に際しても、各開催地の御要望に合わせて、「ビハーラ講習会in高知」では講義を主とした講習となりました。逆に「ビハーラ講習会in近畿」では総合的な講義の後、実習を主に行いました。どちらの講習会も一泊二日で行われました。講習内容を参考資料として載せておきます。
ビハーラ講座開催についての御相談や御質問が御座いましたら、NVN事務局までお問い合わせ下さい。
|
| |
《講義例案》 |
| テーマ | | 時間 | | 講師 |
①「仏教経典、ご遺文に見るビハーラ精神
~法華菩薩行としてのビハーラ活動」 | | 60~90分 | | 山口裕光 奥田正叡 |
| ②「伝日遠『千代見草』に聞く臨終教化」 | | 60~90分 | | 柴田寛彦 村瀬正光 |
| ③「傾聴の基礎と実習」 | | 120分 | | 渡部公容 |
| ④「お見舞い活動の実践」 | | 60~90分 | | 柴田寛彦 |
| ⑤「終末期における医療と宗教」 | | 60~90分 | | 村瀬正光 |
⑥「ビハーラ活動の実践
~高齢者介護の現状~」 | | 60~90分 | | 今田忠彰 |
⑦「実践に活かす知と技
~身近な事例とケアのポイント~」 | | 60~90分 | | 林 妙和 |
| ⑧「グリーフケアの実際」 | | 60~90分 | | 藤塚義誠 |
| ⑨「自死に向き合う」 | | 60~90分 | | 吉田尚英 |
|
| 〈参考資料〉 |
| 「ビハーラ講習会in高知」講習内容 |
| 講義 「仏教経典に見るビハーラ精神」 | | 60分 | | 古河良晧 |
| 講義 「日蓮聖人のビハーラ精神」 | | 60分 | | 山口裕光 |
| 講義 「ビハーラ活動の歴史と現状」 | | 60分 | | 奥田正叡 |
| 講義 「ビハーラ活動とカウンセリング」 | | 60分 | | 渡部公容 |
| 講義 「終末期に於ける医療と宗教」 | | 50分 | | 村瀬正光 |
| 講義 「お見舞いの心得」 | | 50分 | | 柴田寛彦 |
| 講義 「グリーフケア」 | | 60分 | | 藤塚義誠 |
| 講義 「ビハーラ活動の実際」 | | 50分 | | 今田忠彰 |
| 実習 「身近な事例と介護のポイント」 | | 90分 | | 林 妙和 |
|
| 「ビハーラ講習会in近畿」講習内容 |
| 講義 「ビハーラの基礎」 | | 90分 | | 奥田正叡 |
| 実習 「身近な事例と介護のポイント」 | | 110分 | | 林 妙和 |
| 講義 「ビハーラ活動とカウンセリング」 | | 60分 | | 渡部公容 |
| 実習 「ロールプレーイング」 | | 90分 | | 渡部公容 |
|
|
| NVN事務局 | | 住 所 | | 〒763-0046 |
| | | | 香川県丸亀市南条町9-1 宗泉寺内 |
| | 電 話 | | 070-5680-3447 |
| | FAX | | 020-4664-6973 |
| | メール | | info@nvn.cc |
|
|